 悩んでいる人
悩んでいる人「半たわみ性舗装」って何?コンクリート舗装と何が違うの?メリット、デメリットは?土木初心者でよくわからない。。。周囲にも聞けない。。。
こんな悩みに答えます。
本記事の内容
- 半たわみ性舗装とは?
- 半たわみ性舗装の適用箇所
- 半たわみ性舗装の材料
- 半たわみ性舗装の施工方法
- 半たわみ性舗装のメリット・デメリット
- 半たわみ性舗装とコンクリート舗装の違い
- この記事を書いてる人
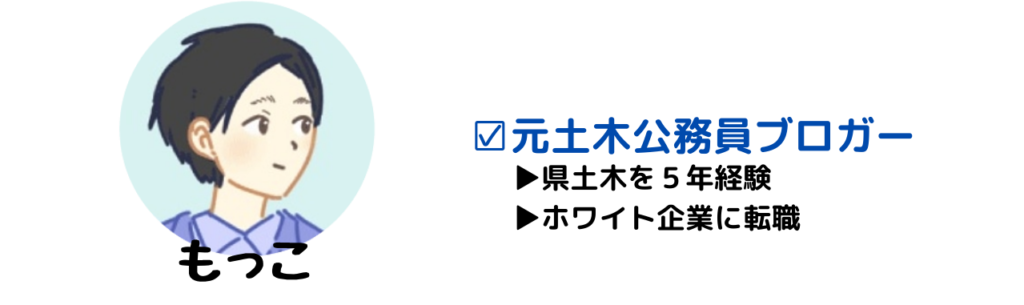
この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。
本記事では、半たわみ性舗装について解説したいと思います。
この記事を読めば、舗装の初歩的な知識が身につきます。
目次
半たわみ性舗装とは?
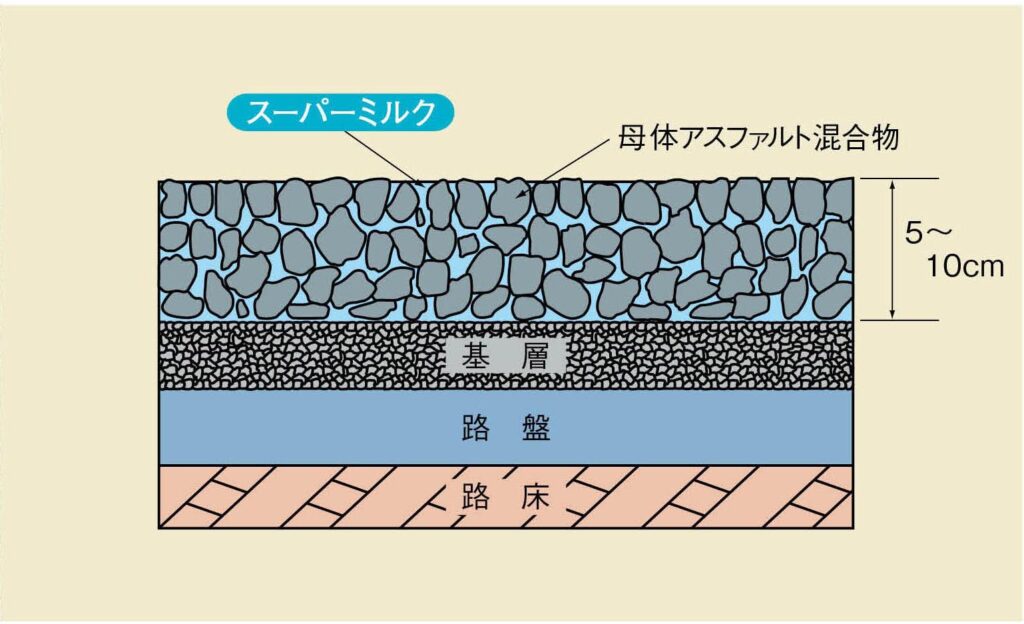
半たわみ性舗装(はんたわみせいほそう)とは、アスファルト舗装とコンクリート舗装の中間的な性質を持つ舗装のことです。
具体的には、すき間の多いアスファルト混合物(開粒度アスファルト)の中に、セメントミルク(流動性のあるセメントペースト)をしみ込ませて固める工法です。
アスファルトの柔らかさ・弾性とセメントの強さ・変形しにくさの両方の性質をもっています。
半たわみ性舗装の適用箇所

半たわみ性舗装は、高い耐久性と耐摩耗性が求められる場所に使われます。
主な適用箇所
- バスレーン、バス停付近
- 工場、ガソリンスタンド
- 交差点、坂道の停止線付近
- 大型車の走行が多い道路
- 物流倉庫の荷さばきエリア
- 港湾や空港の舗装
つまり、重い車が通る、止まる、曲がる場所で威力を発揮します。
半たわみ性舗装の材料
主に以下の2つの材料を使います。
- 開粒度アスファルト混合物(骨材が粗く、すき間が多いアスファルト)
→ 後で液体をしみ込ませるため - セメントミルク(セメント+水+流動化剤など)
→ 上から注入して、アスファルトのすき間を埋めて固める
必要に応じて、ポリマーセメントや特殊添加剤を使うこともあります。
半たわみ性舗装の施工方法

ざっくりいうと、次のような流れになります。
- 開粒度アスファルトの敷設・転圧
→ まず「スカスカ」なアスファルトを敷きます - 冷却・安定期間を置く(温度が高いとミルクが固まる前に流れすぎる)
- セメントミルクの注入(ポンプや散水装置でしみ込ませる)
- 養生(硬化)
→ セメントが固まるまで数日おいてから交通開放
半たわみ性舗装のメリット・デメリット
半たわみ性舗装のメリット
- 耐摩耗性◎ → バスやトラックの走行にも強い
- 耐油性◎ → 油による劣化が少ない
- わだち掘れ・変形が起こりにくい
- ひび割れしにくい(コンクリートより柔軟)
- 薄層でも高強度
半たわみ性舗装のデメリット
- 施工手間が多い
- 材料費・施工費が高い
- 補修がやや難しい
- すべりやすくなることがある(表面処理が重要)
半たわみ性舗装とコンクリート舗装の違い
| 比較項目 | 半たわみ性舗装 | コンクリート舗装 |
| 構造 | アスファルト+セメント注入 | 一体型コンクリート |
| 柔軟性 | あり(たわむ) | なし(剛性) |
| 耐久性 | 高い | 非常に高い |
| 施工期間 | 短め(数日) | 長い(型枠・養生必要) |
| 初期費用 | やや高い | 高い |
| 補修性 | 普通(部分補修は難しい) | 悪い(大がかり) |
| 用途 | 局所補強、バスレーン | 幹線道路、港湾、滑走路 |
moccoblog


ブラック企業、うつ病。どん底からブログ始めて人生変わった話
マジで仕事いきたくない。このまま会社員を続けるのか。いやいや、でも会社員続けないと、妻と子供を養えない。どうしたらいいんだ。あと40年働くなんて無理。 私がブログ…

コメント